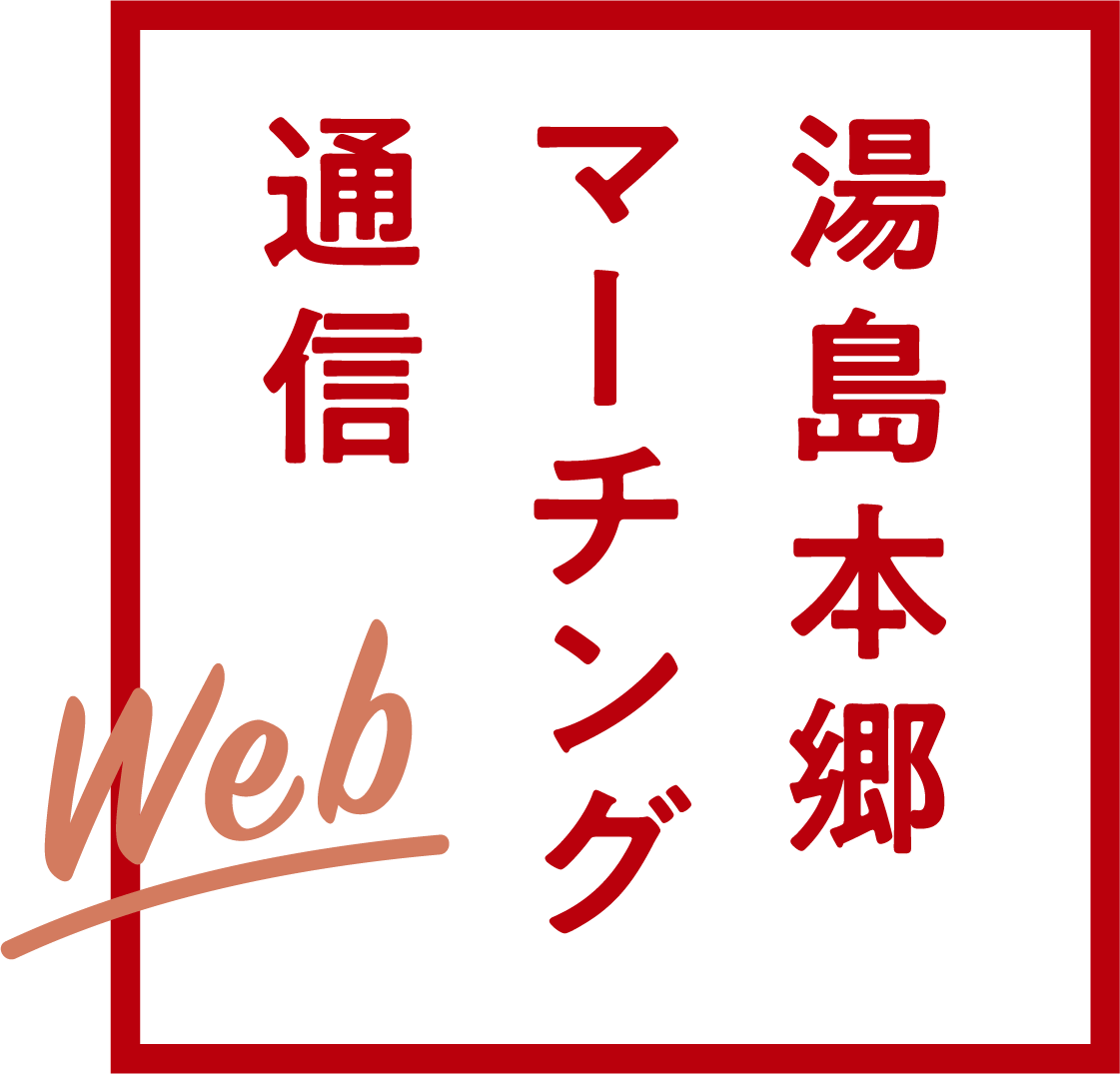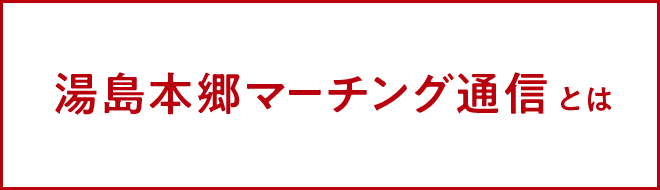2025.05.17
「なまえ」
98号:紗都ちゃんの寺小屋ばなし15

講安寺住職、両門町会町会長 池田紗都さん
桜の花も舞い散り若い息吹が感じられる季節となりました。私事ではありますが、四月に長男が小学校へ入学し、 新一年生として上級生に見守られ新しい毎日を送っております。そこで驚いたのは新一年生達の名前です。漢字表記にされてしまうと読み方もさることながら、性別もどちらなのだろうと考えてしまう名前が多くみられ、名前の変化というものは時代の象徴と言わんばかりと感心してしまいました。法事などの際にお参りする方々のお名前を目にしていますと、五十歳以上のお名前と八十歳以上のお名前にも、当時多いお名前などの変遷が読み取れます。兄弟が四人五人は当たり前な時代では「郎」が多く、「次郎」「三郎」など順番を名前に充てたもの、またもう少し若い世代になると子供の数も減り一人一人に親の名前の一文字をとったものや、こんな人間になってほしいという想いを込めた「志」「大」「雄」などが多い印象です。女性の名前も平仮名やカタカナから、「子」が流行した時代など、時代背景や偏見からその変遷を読み取ることができます。いつの時代も我が子に名前をつける親は皆、愛情をもって悩み悩み付けていたことに変わりはなく、一生そばにある親からの贈り物です。はたまた、こんな名前は嫌だとか、名前負けしそうとか、結婚して姓が変わるときに名前とのバランスを考えてしまうなど、名前というものは無意識のうちに人生を左右しているのかもしれません。仏教語で「名詮自性(みょうせんじしょう)という言葉があります。名前そのものが本来の性質をあらわす、名と実とが一致する、という意味があり、 よく聞く「名は体をあらわす」などしばしば使われます。 本来は、仏の名前はその仏の性質や役割を示すということですが、俗に言う「名は体をあらわす」という人名観は本人の意思によって付けられた名前でないにも関わらず、 本人に内在する個性であるかのように思い込ませ本当の自分を誤解されるような印象で使われることもあります。どんな名前も人の名前は特別なのです。なぜなら他人ではなく親が付けるからです。性質や役割を超越した、 愛情で授かる名前を、大切にしていきたいものです。