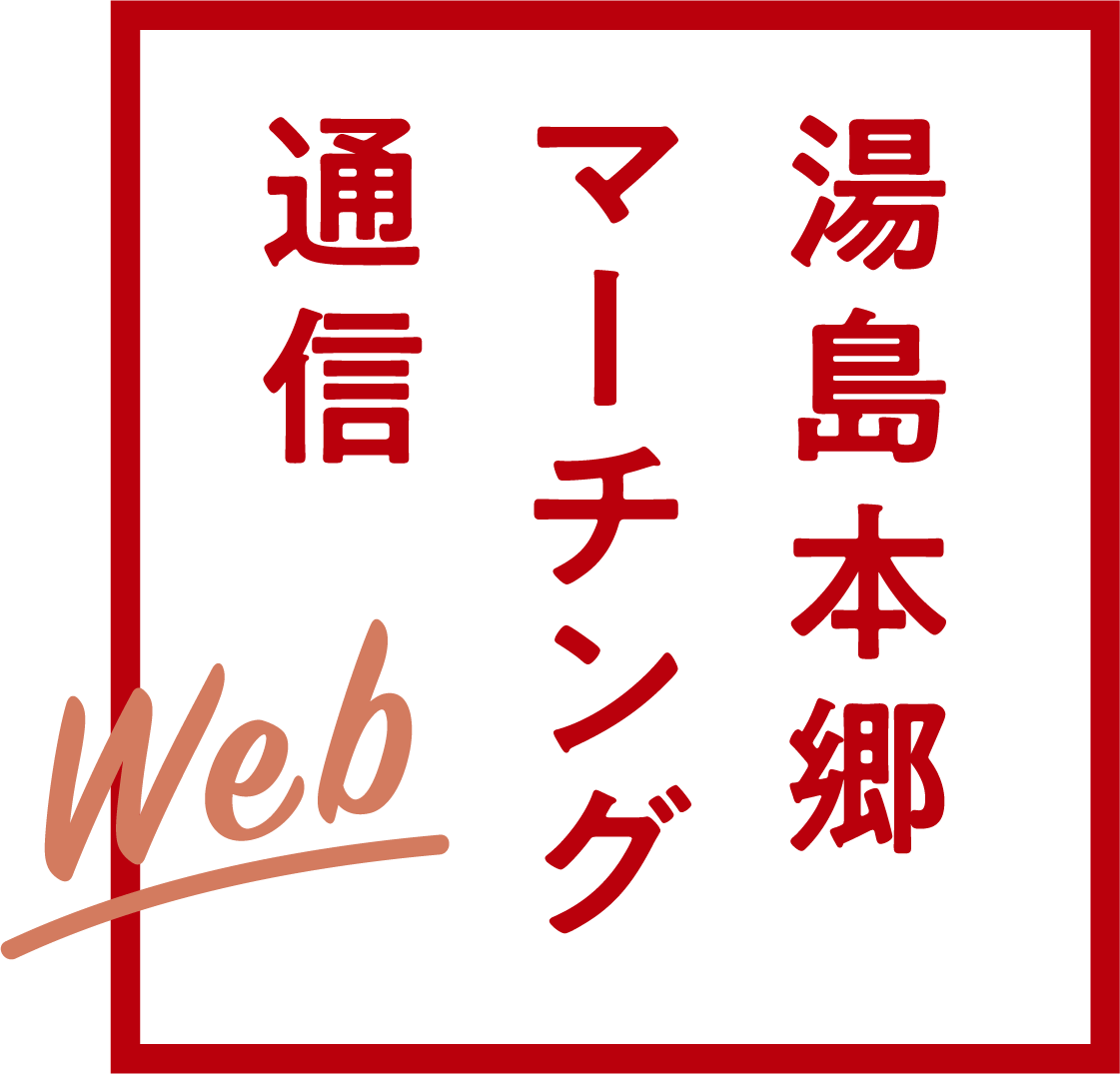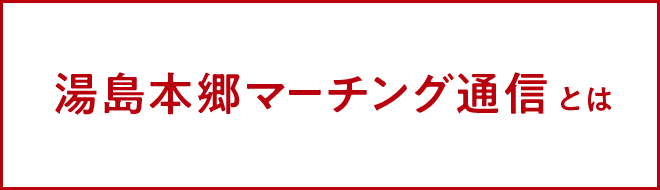2025.09.20
「ともしび」
100号:紗都ちゃんの寺小屋ばなし17

講安寺住職、両門町会町会長 池田紗都さん
例年にない酷暑となり、厳しい夏となりました。ここまでの暑さになりますと自然発火で火事になる場合もあり、 ひと昔前には想像もしていなかった注意を払う必要がでてきました。都会ではコンクリート建造物が多いので自然発火は起こらずとも熱をため込んでしまい大変な暑さになるので、都市計画では緑を増やす緑化も進んでいるようです。
最近は木造建築も防火機能に優れた造りも普及していますが、お寺は昔からの建造物ですし特に火には注意をしなければなりません。しかしお寺に火は不可欠な存在でもあります。法要の際には仏前に火をともし、お墓参りではお線香に火をつけます。ロウソクの火を眺めていると心理的にも癒されますが、仏前にともすロウソクは灯明(とうみょう)と呼ばれ、花や香とあわせて仏さまに対する最も基本的なお供え物ですので、ご供養をする際には必ず必要なものなのです。お釈迦さまの説かれた十二因縁では、無明(この世の理に明るくないこと)が苦の根本原因であるとされています。灯明は、その無明(闇)を照らす智慧の光の象徴として、仏さまに対してお供えされてきました。闇の中にいるようなつらい時は誰にだってあるものです。闇の中で救われたと感じることができるのは光であり、それが何かは十人十色、 さまざまです。家族や友人の言葉、美味しい食事、他人の優しさ︙それさえも見つからない時、仏さまは自灯明(じとうみょう)という教えも説かれました。自分自身をともしびとし、他者に頼るのではなく自分の内なる光である意志や価値観で無明を照らし生きていきなさいということです。他者との支えあいも大切ですが、自分自身の内側に決して消えることのないともしびを持つことこそ、 誰かに優しくできたり自立することができるのではないでしょうか。
仏さまに祈る時はお供えし無明を照らし、自灯明の灯が皆さまにも灯るよう願います。