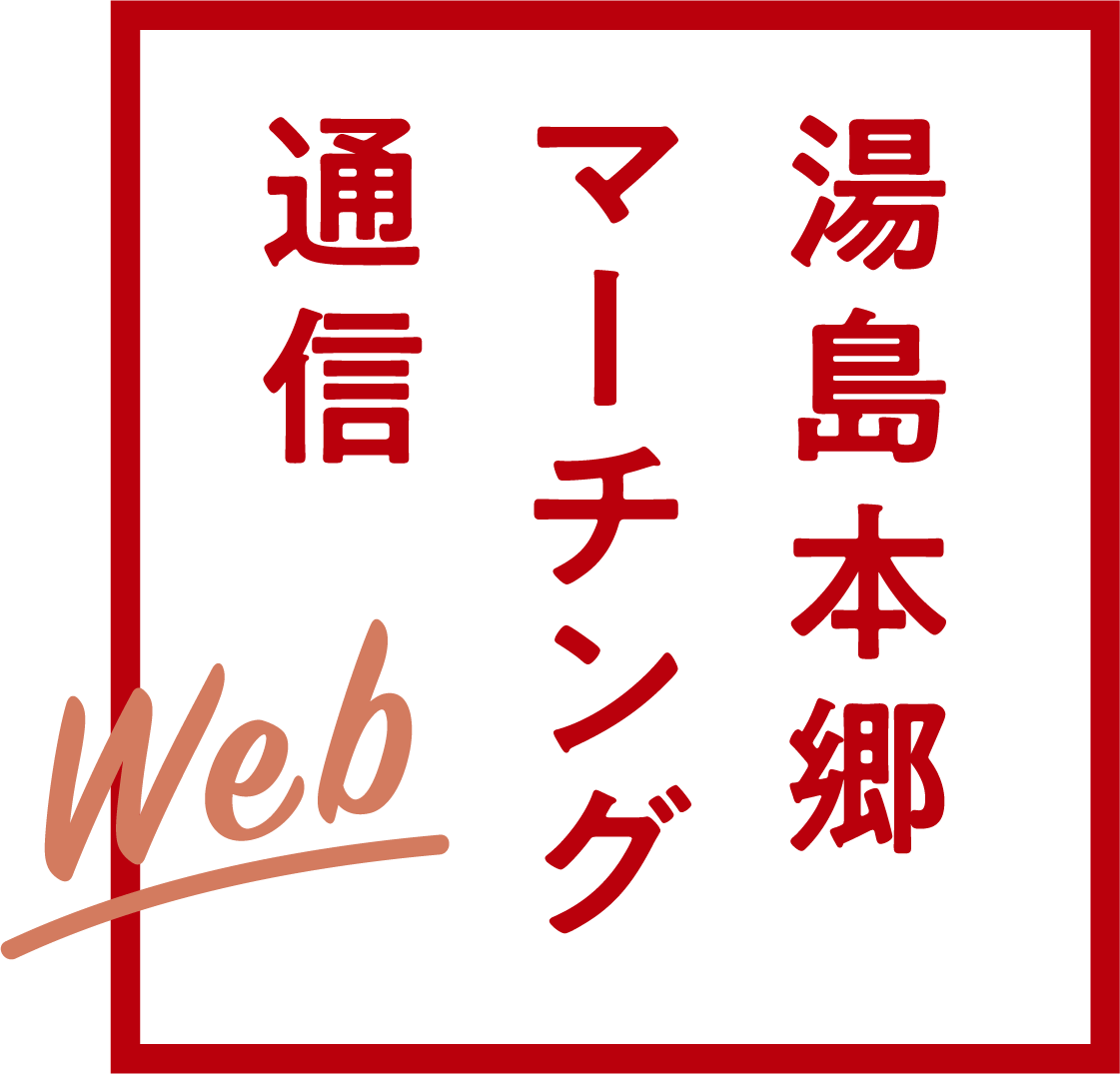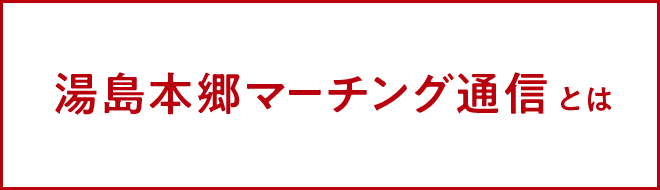2025.07.19
「お盆」
99号:紗都ちゃんの寺小屋ばなし16

講安寺住職、両門町会町会長 池田紗都さん
今年の夏はどれだけ暑くなるのでしょうか。ひと昔前の夏といえば、暑かったものの熱中症という言葉が飛び交うことはなかったように思います。涼を愉しんだ、そんな幼い頃の記憶が思い出されます。懐かしい夏の思い出の中に、 家の玄関前で「迎え火」「送り火」をし、亡くなった祖父母やご先祖さまが帰って来てくれると信じ、おがらに火を焚き「熱い熱い」と文句を言いながら跨いだ記憶が残っています。玄関を開け、立ち昇る煙が家に流れていくのを見ながら「おじいちゃん、おばあちゃんお帰りなさい」なんて思って「今夜は御馳走だ」と下心を働かせていました。
住宅事情が変わり、都心では玄関先やベランダで火を焚くことがしにくくなりましたね。今は火を焚かず、おがらを位牌の前にお飾りし、ほおずきを吊るすことで「お盆」を迎える方も多いと聞きます。形式にはとらわれなくとも、出来る形でご先祖を大切にしたいものです。
お盆の起源は、『盂蘭盆経』というお経にございます。お釈迦さまの弟子の目連尊者は神通力で生前の業により餓鬼道に堕ち苦しむ母の姿に遇い、救いの法をお釈迦さまに求めました。お釈迦さまは「以後毎年この時(旧暦7月15日)に現世の父母のみならず過去七世の父母の為に供養し、長養慈愛の恩に報いよ」と仰いました。今日一般的に行われていますお盆とは7月、または月遅れの8月13日から16日までの間、ご先祖さまを自宅にお迎えし供養することをいいます。『盂蘭盆経』に「過去七世の父母」とありますから、現世の父母だけでなく、その前もその前も命をつないでくださった父母にまで思いを向け、感謝の掌を合わせます。
先祖と聞きますと「顔も知らない」なんて声も聞こえてきそうですが、皆、必ず誰かの子であり、その誰かにも愛する父母がいるわけです。私たちは「生老病死」という苦しみと共に生かされていますが、苦しみばかりではないはずです。幸せな記憶をくれた父母とその父母、またその父母へ、感謝を忘れてはなりません。